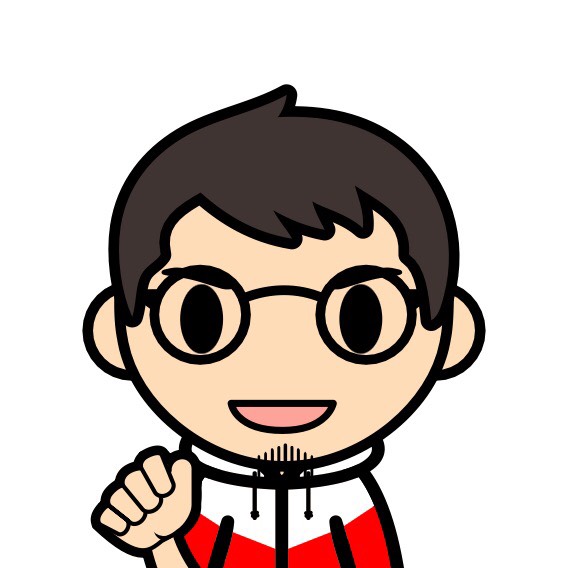
日本のほぼ中心に位置し、山梨県北部から長野県諏訪地方にかけてまたがっている八ヶ岳。
富士山に次ぐ高さと美しい景色が多くの登山客たちの心を魅了しており、毎年多くの人たちが八ヶ岳を訪れています。
初心者向けのコースもあるので、これから登山を始めるという方にも大人気です。
さて、今回はそんな八ヶ岳の歴史についてご紹介いたします。
八ヶ岳の歴史は古く、知れば知るほどより八ヶ岳のことが好きになること間違いなしです!
この記事では、歴史以外にも八ヶ岳の由来や植物の歴史もお伝えしていますので、最後までお見逃しなく!
当サイトGarage Lifeでは八ヶ岳の魅力を記事にまとめて配信しています!ぜひこちらの記事をご覧ください。
ペットと一緒に楽しめる八ヶ岳周辺の観光スポット10選!
八ヶ岳周辺のパワースポット巡りおすすめ7選!
八ヶ岳とは?
八ヶ岳は地形変動ではなく火山活動によって作られた山で、本州の中部山岳を代表する山域です。
特定の一峰を指して呼ぶのではなく、長野県と山梨県にまたぐ山々の総称を八ヶ岳と呼びます。
ほぼ真ん中の位置にある夏沢峠を境に『北八ヶ岳』と『南八ヶ岳』の2つに分類され、一般的には以下の8つの山を指します。
・天狗岳
・横岳
・硫黄岳
・赤岳
・阿弥陀岳
・編笠山
・権現岳
・西山
その他にも、
『南八ヶ岳のみ』
『南八ヶ岳+蓼科山を除いた北八ヶ岳』
『蓼科山も入れた八ヶ岳全体』
といった八ヶ岳の定義もあり、正確には定まっていないようですね。
北八ヶ岳は比較的なだらかな峰が多く、樹林帯が山稜まで続いていたり湖もいくつかあったりします。
それだけではなく、明るく雄大な高原もあるのでとても伸びやかな雰囲気があります。
それに対して、南八ヶ岳は連山で最も標高が高い赤岳をはじめ、横岳・硫黄岳など険しい山々が多いのが特徴です。
コースは様々あり、どのルートへ進んだとしても本格的な登山を楽しむことができます。
また、国内有数のロッククライミングができる岩場もあり、北八ヶ岳とは対象的な山の形をしています。
異なる2つの顔を持ち合わせていることは八ヶ岳の大きな魅力ですね!
また八ヶ岳連峰は、優れた自然の風景地であることから1964年に国定公園としても認定されています。
八ヶ岳の由来とは?
八ヶ岳の名前の由来には、様々な諸説があります。
最も言われているのは、たくさんの峰を持つという意味から数字の『八』を用いて八ヶ岳と名付けたという説です。
また、山々が連なっていることから『八百万(やおおろず)』の神がいると言われており、それぞれ『八』『百』『万』という文字には『たくさん』という意味が込められていることからその名が付きました。
その他にも、
・いくつもの谷筋が見えることで『谷戸』という言葉からきている
・山麓から見える赤岳・横岳・硫黄岳・編笠山・阿弥陀岳・天狗岳・西岳・権現岳・編笠山の八つのピークを総称したもの
などの説もあるようです。
『八ヶ岳』と呼ばれるようになった時期は定かではありませんが、1645年に作られた信濃の国の書物に『八ヶ岳』という山名が記されていたことから古くより呼ばれていたことが分かりますね!
八ヶ岳の歴史を詳しく解説!

八ヶ岳の歴史は古く、噴火活動が始まったのは約130万年前からと言われています。
初期の噴火が起きたのは北八ヶ岳の蓼科山周辺で、ほぼ同時期に古麦草火山と古八柱火山でも噴火が起きていました。
北八ヶ岳周辺の火山活動が落ち着き、約30万年前から南八ヶ岳周辺でも火山活動が始まったとされています。
場所は古阿弥陀岳火山で、大きな噴火活動が長期にわたって起き、どんどんと大きく成長していきました。

当時の山体を現在の地形から復元してみると、富士山と同じような地形をしているということが分かり、標高は約3,400mほどあったと考えられているようです。
その他の山の噴火記録は残っていないため諸説ありますが、888年に天狗岳が崩壊して松原湖が誕生しました。
ただ、崩壊の原因は未だに解明されておらず、噴火または地震と言われていますが証拠がないので現在も謎に包まれています。
そして、北横岳は近年の研究により、地質的に新しい溶岩があったということが分かり、およそ600年~800年前の噴出ではないかと推測されています。
縄文時代~江戸時代にかけての八ヶ岳

画像引用元:ちの旅
縄文時代、八ヶ岳の西南方面は国内で最も栄えていた場所として知られていました。
八ヶ岳には、黒曜石という生活に欠かすことができない石器の材料があり、当時は日本で最大と言われるほどの名産地として話題になっていました。
縄文時代からすでに八ヶ岳周辺は繁栄しており、それに伴い規模も大きくなっていったのです。
弥生時代、気候が下がったことが原因で住人たちが温かい場所へと移動し諏訪地方を離れていきました。
古墳時代~奈良時代にかけて、諏訪地方は再び繁栄し八ヶ岳の山麓は牧場へと進化していきました。
※八ヶ岳周辺の牧場についてはこちらの記事をご覧ください!
八ヶ岳の牧場特集!開放的な牧場でのんびりと過ごそう。
戦国時代になると、甲斐国の武田信玄によって諏訪地方が侵略され、八ヶ岳の道も変化が起きます。
武田信玄は信州越後を侵略する際、八ヶ岳の南麓~西麓にかけての道を軍用道路として開発しました。
棒のようにまっすぐ伸びた道であることから『棒道』と呼ばれ、現在はハイキングコースとして多くの登山客に親しまれています。
時は流れ、江戸時代に入ると八ヶ岳は地元の人たちにとって身近なものになっていきました。
集落が増え、それに伴って高地の開発が進み広い土地が開拓されていきました。
1700年代には、本沢温泉が開発されたり硫黄の採掘が行われたりして仕事をするために八ヶ岳へ来る人たちが増えていきます。
※八ヶ岳周辺の温泉についてはこちらの記事で詳しく説明しているのでご覧ください。
八ヶ岳でおすすめの温泉!日帰り・泊まりで楽しめる観光スポットや旅館を紹介!
その後、山中で修行をする修験者も現れ、山の頂上に神社が分社されたことで八ヶ岳を信仰する人たちも出てきました。
八ヶ岳周辺の神社についてはこちらをご覧ください。
【八ヶ岳周辺の神社特集】心落ち着くおすすめ神社を11選紹介!
明治時代~昭和にかけての八ヶ岳

八ヶ岳に一般の人たちが登り始めたのは、明治時代の中期頃です。
1905年に、俳句を作ってお互いに発表しあう会が結成され、登山客が一気に増加しました。
大正時代にかけては、測量士や生物学者、地質学者など様々な分野の研究者たちが山に登り、八ヶ岳の研修を開始しました。
八ヶ岳は他の山に比べて登りやすいため、研究者たちも山の研究がしやすかったようです。
昭和になると研究者だけではなく、山愛好家や学生らも山登りをするようになりますが、1941年に起きた太平洋戦争により登山客は激減していきました。
終戦後は、観光地として八ヶ岳が注目を浴び、昭和40年~50年代にかけて登山ブームが起きました。
以降は、ブームが落ち着いたと同時に登山客は減りますが、クライミングや健康ブームなどの影響で徐々に増え、例年多くの人たちが訪れる人気スポットとなっています。
八ヶ岳の登山についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
八ヶ岳周辺の登山特集!難易度やおすすめポイントを紹介!
八ヶ岳と富士山の伝説!

八ヶ岳には、古くから『八ヶ岳は富士山よりも高かった』という言い伝えがあります。
まだ八ヶ岳と富士山が活火山だった頃、八ヶ岳の神様である磐長姫(いわながひめ)と富士山の神様である木花柵耶姫(このはなさくやひめ)は、互いに自分の山の方が高いと言っていました。
ある日、どちらの山が高いかで喧嘩が起こり、背比べをすることになりました。
神様同士の喧嘩を見かねた如来様が、喧嘩を止めようと八ヶ岳の峰から富士山の峰まで樋をかけ、水を流したそうです。
水は八ヶ岳から富士山の方へと流れ、その結果『八ヶ岳の方が高い』ということになりました。
しかし、負けず嫌いの木花柵耶姫は納得せず、怒りを露わにし、思わず八ヶ岳を蹴とばしてしまいました。
蹴とばされた八ヶ岳は8つに割れて現在のような形になり、富士山よりも低くなったと言われています。
八ヶ岳と富士山の背比べの言い伝えは、今もなお裾野に住む人たちの間で受け継がれ続けています。
ちなみに、八ヶ岳と富士山それぞれの噴火史を地質学的観点から見た時の研究結果も出ています。
約25万年前は、八ヶ岳が約3,400m・富士山が2,400mと八ヶ岳の方が約1000mほど差があり、約10万年前は赤岳が2,899mに対し富士山の標高は2,700mとなっていました。
約1万年前になると、富士山の火山活動が活発になり、徐々に高度が上がり3,776mにまで到達し日本一の高い山となったのです。
八ヶ岳に高山植物が残るまでの歴史

八ヶ岳は南アルプスの北岳と北アルプスの白馬岳とともに、高山植物の三大宝庫と言われています。
高山植物は、今から約100万年ほど前に幾度となく襲来した氷河期に耐えたことで、寒さに強いという特徴があります。
約1万年前に氷河期が終わりを迎え温かい気候となりましたが、植物たちは山岳地帯に種を残し保存をはかっていました。
八ヶ岳周辺の特徴として冬は基本的に雪が少ない気候なので、乾燥に強い種が残りました。
今では約1000種もの高山植物があり、クロユリやオミナエシ、唐松にコマクサなど様々な種類の植物が咲いています。
さらに、八ヶ岳特有の『ヤツガタケキンポウゲ』や『ヤツガタケタンポポ』など新しい植物も多数あり、白馬岳に次いで稀品種が多い山として有名です。
まとめ:歴史を知ってもっと八ヶ岳を好きになろう!

今回の記事のまとめは以下の通りです。
長い年月をかけて自然が作り出した八ヶ岳。
8つある山にはそれぞれ深い歴史があり、地形や標高などにはすべて意味があります。
八ヶ岳から見える景色が美しかったり自然に癒されたりするのも良いですが、歴史を感じながら登山を楽しむのもアリなのではないでしょうか。
先人たちが努力して培ってきたものを守り、そして育てていき次世代にもこの歴史を繋いでいきたいものです。























