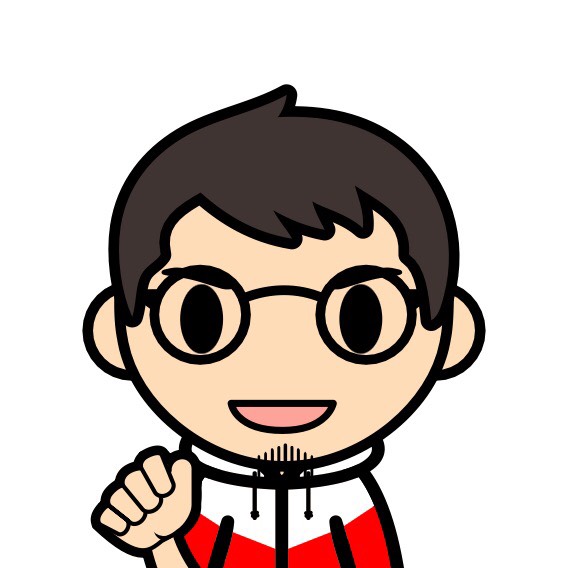
長野県北部にある白馬村にはたくさんの山があり、周辺の山岳地帯として有名な「八ヶ岳」に負けず劣らず、国内でも有数の登山スポットとして有名です。
そんな白馬では1年を通して国内外から多くの登山客が訪れますが、特に注目を集めているのが冬の時期での登山です。
冬の時期は白馬村にある山々が真っ白な雪に覆われ、神秘的な景色を望むことが出来ます。
この記事では、白馬村周辺で雪山登山をするのにおすすめなスポットをご紹介していきます!
どの山も標高が高く、本格的な登山を楽しむことができますよ。
また記事の後半では、雪山を登る際の注意点や必須アイテムについて紹介していますのでぜひ最後までご覧ください!
八ヶ岳周辺のおすすめ登山スポットはこちらで紹介しているので合わせてご覧ください!
【この記事で紹介する雪山】
この記事で紹介する雪山の場所を以下の地図にマッピングしました!
①雪山登山が初めての方におすすめの『唐松岳』

唐松岳は白馬岳と五竜岳の間にある標高2,696mの山で、雪山登山の初心者さんにおすすめとなっています。
その理由としては以下の点が挙げられます。
- 白馬八方尾根スキー場のゴンドラとリフトを乗り継ぎ標高1850mにある八方池山荘まで上ることができる。
- 登山者が多く、トレース(足跡)があることが多い。
- 難しいコースが少ない
難しいポイントがないことに加え、ゴンドラとリフトで標高1,850mの場所まで行き、そこからスタートできるのは嬉しいですね。

また、スタート地点から白馬岳や鑓ヶ岳、杓子岳といった山々を望むことができるのも魅力的です。
そして、山頂からは黒部渓谷や立山連峰、五竜岳など迫力満点の景色を一望できます。
天気が良ければ、富士山・南アルプス・八ヶ岳・日本海も見ることができるので、ぜひ晴れた日に足を運んでみてください。
■唐松岳の概要■
| 所在地 | 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村富山県黒部市 |
|---|---|
| 登山難易度 | 初心者~中級者 |
| 標高 | 2,696m |
②日本百名山に選ばれている『白馬岳』

白馬村を代表する山といえば、やっぱり白馬岳です。
白馬岳は標高が2,932mあり、南北方面に連なっている後立山連峰の北部に位置しています。
長野県・富山県・新潟県の3県にまたがっており、白馬鑓ヶ岳・杓子岳と合わせて白馬三山とされています。
まさに、北アルプスを代表する山と言えるでしょう。
白馬岳には豊富な高山植物もあり、美しい花を見ることができる山としても有名です。
そのため、冬だけではなく様々な種類の花が咲く夏の時期にも多くの登山客で賑わいます。
白馬岳の山頂からは、南アルプス・中央アルプス・八ヶ岳・日本海などの絶景を眺めることができます。

比較的、白馬岳は長距離のコースが多く、登山入り口である猿倉から頂上まで約6時間15分が目安です。
難易度は中級者以上となりますが、栂池高原よりロープウェイを利用して行くコースは、難しいポイントが少なく初心者にも向いています。
■白馬岳の概要■
| 所在地 | 〒399-9301 富山県下新川郡朝日町北城 |
|---|---|
| 登山難易度 | 中級者~上級者 |
| 標高 | 2,932m |
③武田信玄の家紋に似ている雪形がある『五竜岳』

五竜岳の標高は2,814mで、後立山連峰の中の一つです。
白馬岳と同じく稜線を境に片方がなだらかで、反対側が切れ落ちた地形をした非対称となっています。
東側には遠見尾根があり、その光景はまさに壮大です。
五竜岳の山体は大町市(長野県)と黒部市(富山県)にまたがっており、頂上付近は富山県に位置しています。
長野県側から見ると、岩峰を連ねた迫力ある山々を眺めることが可能です。
五竜岳頂上の左下にみえる大きな菱形の岩壁は、白馬周辺を支配した戦国武将、武田信玄の家紋『四つ割菱』に似ていることで有名です。
五竜岳登山のコースは、以下の2つが主な一般的ルートとなります。
- 白馬五竜スキー場のゴンドラリフト(テレキャビン)を利用して遠見尾根部分から登山するルート
- 八方尾根にあるゴンドラに乗って唐松岳を通って登山するルート
上記の一般的なルート以外にも、八峰キレット(後立山連峰の五竜岳と鹿島槍ヶ岳の間位置する)を通っていくコースもユニークなので上級者に人気です。
また、行きの登山口とは違う場所へ帰ってくるという登山者も多く、様々な楽しみ方ができます。
■五竜岳の概要■
| 所在地 | 〒938-0174 富山県黒部市長野県大町市 |
|---|---|
| 登山難易度 | 中級者~上級者 |
| 標高 | 2,814m |
④トレッキングコースとして人気の『小遠見山』

小遠見山は五竜岳へ向かう途中にある山で、トレッキングコースとして多くの登山客が山登りを楽しんでいます。
小遠見山へ登るためには、地蔵の頭という場所からスタートするのが一般的なルートとなります。
地蔵の頭は、白馬五竜テレキャビン終点駅のアルプス平で降りて、アルプス展望のリフトへ乗るとたどり着くことが可能です。
スタート地点から登山を開始し、
- 地蔵ケルン(約1,676m地点)
- 見返りの平(約1,740m地点)
- 一ノ背髪(約1,892m地点)
- 二ノ背髪(約1,950m地点)
といった各ポイントを通過すると、標高2,007mの小遠見頂上へと到着します。

地蔵の頭から頂上までの時間は約1時間30分ほどで、登山初心者さんでも登りやすいコースとなっています。
ただし、小遠見山頂上より奥の五竜岳へと続く道は険しいため、アイゼンやピッケルなどは必須アイテムです。
小遠見山頂上からでも爺ヶ岳をはじめ、五竜岳、唐松岳といった山々の大パノラマを観賞できるので、満足できること間違いなしです。
■小遠見山の概要■
| 所在地 | 〒399-9211 長野県大町市神城 |
|---|---|
| 登山難易度 | 初心者~中級者 |
| 標高 | 2,007m |
⑤日本最大級のスケールを誇る『白馬大雪渓』

白馬大雪渓は、白馬岳と杓子岳の間にできた雪渓です。
標高差約600m・全長3.5kmもあり、国内最大級の雪渓として知られています。
また、剣岳の剱沢大雪渓(富山県)・針ノ木岳の針ノ木雪渓(長野県大町市)とともに日本三大雪渓にも選出されているほど有名な場所です。
白馬大雪渓も白馬岳の途中にあるのですが、雪渓の神秘的な景色を一目見ようと多くの人たちが雪渓の遊歩道まで登りに来ます。

白馬岳のメイン入り口である猿倉から白馬岳の基部となる白馬尻には、約1時間30分ほどで到着します。
白馬尻には『白馬尻小屋』という施設があり、うどんなどの軽食が販売されておりゆったりと休憩することが可能です。
白馬尻から徒歩約15分ほど歩くと白馬大雪渓へと到着します。
猿倉から白馬大雪渓までの道は整備されているので、気軽にアルプスの絶景を眺めながら登山ができます。
大雪渓から白馬岳へと進むのであれば、30~40リットルほどのザック・登山靴・アイゼン・ヘルメット
などの装備をしなければ難しいでしょう。
■白馬大雪渓の概要■
| 所在地 | 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 |
|---|---|
| 登山難易度 | 初心者~中級者 |
| 標高 | 1,550m~1,700m |
⑥大自然が造りだした八方池が観賞できる『八方尾根』

唐松岳付近の尾根から延びる八方尾根。
唐松岳より四方八方に尾根が広がっている様からその名が付きました。
八方尾根には八方池という美しい池があるのですが、ほとんどの方が八方池をゴール地点として登山をします。
ゴンドラリフトを乗り継いで、八方アルペンラインの終着地にある八方池山荘から八方池を目指すコースが一般的です。

ゴンドラとリフトで標高1,830mの場所まで一気に登ることができ、標高2,060mの八方池までは片道約1時間30分ほどで到着します。
八方池までの道は整備されていて、軽装備でも登ることができるので気軽にトレッキングが楽しめます。
また、道の途中には日本百名山に選ばれた山々を一望できるスポットが何か所もあり、晴れた日には第1ケルンより富士山を眺望できます。
冬の時期は空気が澄んでいて自然の景色がより美しく見えるので、一見の価値ありです。

そして、ゴールである八方池も晴れた日には池の水に白馬三山が映し出され、神秘的な景色を観賞できます。
まるで鏡のように映った白馬の山々を見たら、驚くこと間違いなしです。
八方池は人工池ではなく長い年月をかけて自然が造りだした池なので、その迫力に圧倒される登山客が非常に多いです。
■八方尾根の概要■
| 所在地 | 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 |
|---|---|
| 登山難易度 | 初心者~中級者 |
| 標高 | 2060m(八方池まで) |
⑦山頂テラスのある白馬岩岳(岩茸山)

白馬岩岳の標高は1,289mと他の山に比べたらコンパクトではありますが、山頂からの景色はかなりの絶景です。
山頂まではゴンドラが出ていますが、トレッキングで向かうこともできます。
山麓の西山グラウンド手前に登山入口があり、信濃路自然歩道を通って片道約1時間30分ほど歩くと山頂に到着です。
コース内には急な登り道や岩場などはなく、初めて登山する方でも安心して山登りができます。
また、道の途中には天狗の庭・犬の寝床・さかき岩という3つの展望台があり、北アルプスの風景を眺めながら休憩できたりします。
山頂付近まできたら、ぜひ『ねずこの森』と呼ばれる散策路に立ち寄ってみてください。

ねずこの森では、自然を感じながらスノーシュートレッキングをすることができます。
そして、岩岳山頂へ到着すると「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」というオシャレなカフェレストランが待ち構えています。
開放感あふれるカフェでは、この場所でしか味わうことができないパンやサンドウィッチが勢ぞろいです。

広々としたテラスでコーヒーなどもいただくことができるので、一面真っ白な白馬の世界を見ながらのんびりできます。
美しい山の世界を目で見て、おいしい料理を味わい、自然の空気を感じる・・まさしく五感で楽しむことができる場所です。
美味しい食事と素晴らしい景色を眺めて、日頃の疲れを癒しちゃいましょう。
■白馬岩岳の概要■
| 所在地 | 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 |
|---|---|
| 登山難易度 | 初心者~中級者 |
| 標高 | 1,289m |
雪山登山をする時の注意点

登山には危険がつきものと言われていますが、特に雪山の登山にはたくさんの危険が潜んでいます。
雪山登山で起こりうることを把握し、事前に対策を練っておかなければ危険ですので、この記事でしっかりと知識を付けておきましょう。
雪山登山をするうえで、最低限注意しておくべきことは以下の7つです。
- 山の斜面に積もった雪が圧力で崩れる『雪崩』
- 雲や雪で視界が見えなくなり、距離感や方向感覚が分からなくなる『ホワイトアウト』
- 夏の登山ルートとは異なる冬専用コースが設けられたことによって起こる『道迷い』
- 雪原に反射した紫外線を浴びすぎて、目の角膜が炎症する『雪目』
- 体内の熱と外に放出される熱のバランスが崩れ、体温が35℃以下に下がる『低体温症』
- 長時間低温の環境にいることで血流が悪くなり、細胞が破壊される『凍傷』
- アイスバーンになった場所で躓いたり踏み抜きによって起こる『転落・滑落』
上記の中でも『転落・滑落』には、かなりの注意が必要です。
山頂や山の尾根などで風下方向にできる雪の塊を雪庇(せっぴ)と呼ぶのですが、非常にもろくて実際の登山道と区別が難しいです。

尾根を歩く際に気が付かずに雪庇を踏み抜くと、そのまま下へと滑落してしまう恐れがあります。
ですので、雪山登山は常に『立木の位置など周辺の情報から安全なルートを導き出せる人』と一緒に行うようにしてください。
雪山登山で必要なアイテム

安全に雪山登山をするためには、事前にしっかりと装備やアイテムを揃えておくことが重要です。
冬用のウェア上下・防寒着・手袋・靴下・帽子・ネックウォーマーといった装備の他、以下のようなアイテムも必ず持参するようにしましょう。
- 保温性バツグンの登山靴
- 水筒・行動食(パンやナッツ、チョコレートなど)
- 雪焼け対策として活躍するタオル
- 紫外線から目を守るゴーグル
- 滑落防止のためのピッケル
- 登山靴の裏に装着して滑り止めにするアイゼン
- 転倒した時などに頭を守るためのヘルメット
- 長距離を歩く際、体の負担を和らげるために持つトレッキングポール
雪山登山をするためのアイテムは、ただ用意するだけでは意味がありません。
ピッケルやアイゼン、トレッキングポールなどのアイテムは使い方を知っておく必要があります。
「いつ、どんな状況の時に使うべきものなのか」を把握しておくことが大切です。
登山をしながら冬の山々をご堪能あれ!
冬の登山といえば、険しいイメージを持つ方が多いかと思いますが、白馬の雪山には登山初心者でも登りやすい山がたくさんあります。
登山をしながら自然の風を肌で感じることができたり、白馬周辺にある壮大な山々を眺めたりと冬の時期でしか味わえない体験ができます。
また、ゴンドラやリフトから見る景色も最高ですので、ぜひ様々な角度・距離から白馬の山々を眺めてみてください。

















