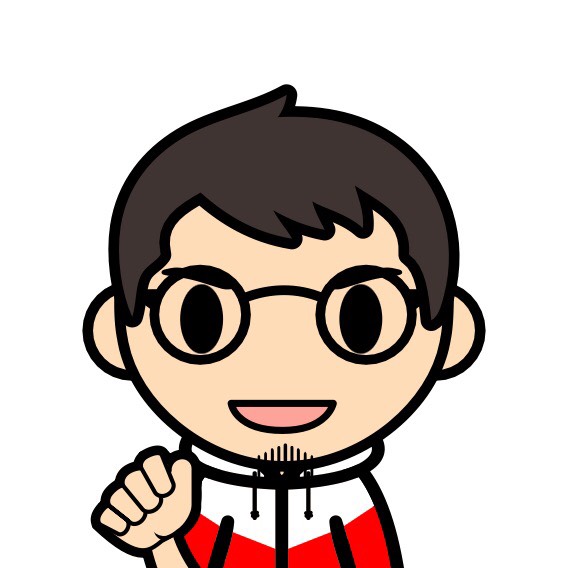
住む場所に縛られることなく、自由に移動して暮らしたい。そんな思いをお持ちの方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
近年注目を浴び始めたトレーラーハウスは、その思いを実現可能です。
しかもトレーラーハウスは車両扱いのため、固定資産税が不要となるため節税にはもってこいです。
本記事では、トレーラーハウスを使った節税できる理由を3つと、利用例や購入時の注意点について徹底解説しています。
購入を検討中の方や節税方法をお探しの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
トレーラーハウスは節税できる

トレーラーハウスを検討されている方の中には「節税になるらしい」という話を聞いたことがある方も多いはず。
確かにトレーラーハウスを上手に利用すれば思わぬ節税につながることもあります。
ただし、トレーラーハウスを車両と建物のどちらで認定するかによって、得られる節税効果は異なります。
次の項目から、それぞれの節税になる理由を解説します。
トレーラーハウスが節税できる理由とは

トレーラーハウスが節税できる理由は次の3点です。
- 固定資産税がかからない
- 建築物とした場合、固定資産税は6分の1になる
- 減価償却期間が短い
減価償却期間とは、購入した家や機械のなどの資産が、時間が経過したことによって減少する資産価値を費用に計上する会計手続きのことです。
このように、節税効果を利用して資産運用として活用する方もいるようです。
次から、詳しく解説します。
トレーラーハウスが節税できる理由①固定資産税がかからない
トレーラーハウスは、車両として認められると固定資産税がかかりません。また、都市計画区域に課税される「都市計画税」の支払いもないため、節税できます。
トレーラーハウスが車両として認められる条件は後述しますが、そのなかの1つが「ライフラインが土地から取り外しができること」です。
トレーラーハウスは自走できれば車両として扱われます。エンジンがなく公道を走行できない車両なら、自動車税さえも不要です。
しかし、設置や撤去でトレーラーハウスを移動させたいときは、公道を走れるように、自動車税の支払いや車検・ナンバー取得などの手続きが必要です。また、これらの費用がかかることを想定しておいてください。
トレーラーハウスが節税できる理由②建築物とした場合、固定資産税は6分の1になる
トレーラーハウスを建築物とした場合、固定資産税が6分の1となる場合があります。ただし、トレーラーハウスを設置している場所が自分の土地である場合に限ります。
土地の固定資産税は、更地のままだと固定資産税が高くなります。しかし、建物と一体化して使用した場合、土地の広さが200㎡以下は更地の6分の1、それ以上は3分の1にまで減税されます。
トレーラーハウスが建物として扱われる条件の1つに「土地に定着していること」というものがあります。
自身の土地にトレーラーハウスを設置している方は、車両として設置する場合とどちらの方が安くなるか、調べておくと良いでしょう。
トレーラーハウスが節税できる理由③減価償却期間が短い
トレーラーハウスは、減価償却期間が短いため、節税効果があると言われています。通常、建物の減価償却期間は20年を超えます。しかし、トレーラーハウスを車両扱いにすると4年になります。
また、トレーラーハウスを店舗やホテルといった事業に使用したい方は、さらなる節税効果が狙えます。節税分でトレーラーハウスの内装を充実させることも可能です。
トレーラーハウスの節税以外のメリット

トレーラーハウスの節税以外のメリットは、資産運用として活用できるところです。トレーラーハウスは、約500万円あれば投資可能で、アパートやマンションの経営と比較すると初期費用がからないと言えます。
そこで、トレーラーハウスを購入して、事務所として貸出したりホテル経営をしたり投資として活用する方もいます。一般的な住居と同様の家具や家電が使えるため、内装でオリジナリティを出すことも可能です。
また、トレーラーハウスは移動や撤去がしやすいため、万が一売却したくなったときも問題が少ないです。
トレーラーハウス運用には縛りがある

節税するためのトレーラーハウス運用はある程度縛りがあります。下記で詳しく紹介していきます。
トレーラーハウスの設置基準
トレーラーハウスは車両付きの家ですが、家にタイヤを付ければトレーラハウスになるわけではありません。
車両として利用する場合は、公道を走行できる安全性も重要です。
トレーラハウスは法律上で明確に定義されています。次から、トレーラーハウスの車両扱いされる条件と建築物扱いされる条件を詳しく解説しています。
車両扱い
トレーラーハウスは「いつでも移動できる状態」でないと車両として認められません。
「日本トレーラーハウス協会」に記載があります。
- 随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
- 土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
- 適法に公道を移動できる自動車であること。
自動車等(適法に公道を移動できるトレーラーハウスを含む)が土地に定置して、土地側の電気・ガス・水道等と接続した時点で建築基準法の適用を受けます。
逆に土地側のライフラインと接続しない場合、自動車として扱われ、建築基準法の適用を受けません。
(参考:日本トレーラー協会|法的基準について)
また、道路運送車両法では「車幅2.5m、車高3.8m、車長12m」以上のサイズをトレーラーハウスと認めている為、このサイズに到達しないものはトレーラーハウスとして認定されません。
建築物扱い
建築物扱いされるトレーラーハウスは、次のような条件です。
建築物に該当する例(建築基準法の適用を受けるもの)
- 随時かつ任意に移動することに支障のある階段・ポーチ・ベランダがあるもの
- 給排水・電気・ガス・電話・冷暖房等の設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が工具を使用しないで取り外すことができないもの
- 車輪が取り外されているもの、走行するに十分な状態に保守されていないもの
- 設置場所から公道に至るまでの通路が連続して確保されていないもの
トレーラーハウスを設置する際は、以上のことに気を付け、利用目的を明確にすることが必要です。
トレーラーハウスとは?活用方法を解説!

画像引用元:yadokari
トレーラーハウスとは簡単に説明すると「車のタイヤが付いた土台の上にある家」です。
似たようなものにキャンピングカーがありますが、キャンピングカーとは明確に違うものです。
トレーラーハウスは自力で移動することはない工作物と言えますが、キャンピングカーは「移動すること」に重点を置いているため、キャンピングカーの家具は極力コンパクトな作りになっています。
一方のトレーラーハウスは「生活する場所としての機能」に重きを置いています。ですから、本格的なキッチンやお風呂などの水回りや家具などを充実させることも可能です。
トレーラーハウスは基本的に住宅と同じ構造のため、電気・水道を引くことが可能です(キャンピングカーはタンクに水をため、電気は充電式か発電機を使用します)。
そのため、キャンピングカーでは実現できない、さまざまな使い方ができます。
「さまざまな使い方ができる」ということこそトレーラーハウスの特徴にして魅力です。
なお余談ですが、トレーラーハウスという呼び名は和製英語。英語ではモービル ホーム(移動住宅)などと呼ばれます。
では、トレーラーハウスの活用法を具体的に見ていきましょう。
住居としての利用
 画像引用元:Tiny Home
画像引用元:Tiny Home
トレーラーハウスには、生活で必要なアイテムはすべて、そろっているため、住居として問題なく利用できます。
一般的な建物ではなく、あえてトレーラーハウスを住居として選択している方も、日本国内に少なからず存在しています。
「住み心地が気になる!」という方は実際に住んでいる方がSNSやブログで情報を発信しているため、チェックしてみても良いでしょう。そこからは、一般的な住宅と全く変わらない暮らしぶりがうかがえます。
むしろ、普通の家には無い不思議な楽しさが伝わってくるほどです。
店舗としての利用

画像引用元:Rumspringa
トレーラーハウスを店舗として利用するという方も数多くいます。
タイヤ付きの家ですから、見た目のインパクトは抜群。SNSなどにアップされ、何もせずとも拡散していきます。そのため、あえてトレーラーハウスを選択するという方がいるのかもしれません。
またトレーラーハウスには税制上のメリットがあり、店舗としての利用が多いことも理由の一つです。
カフェなどの飲食店として

画像引用元:ルクラ公式サイト
入ってみたいと思わせる外観、こだわりの詰まったおしゃれな内装、決して広いとは言えないけれど、十分なスペース。それを何に使うのかと言えばやはりカフェのような飲食店です。
広すぎないスペースが、一人でお店を切り盛りしたいという方にはぴったりと言えます。
散歩中やドライブ中にトレーラーハウスで営業しているカフェを見つけたら「入ってみたい」と思うでしょう。
カフェとしての利用のほか、クラフトビールを提供するビアバーや、美容院として利用している方も。
いずれも「インパクトのある外観」を上手に利用しています。
民泊施設としても大人気!

画像引用元:Blue Baloo Tiny House
「問題なく住める」という、トレーラーハウスならではの特性を生かせしているものが、民泊としての利用です。
新しく建物を立てて民泊を始めるというのは大変ですが、トレーラーハウスであれば、金銭的な面でも比較的スムーズに始められます。
また広すぎないため、掃除やメンテナンスがしやすいというのも民泊に利用しやすいポイントだと言えます。
「トレーラハウスの住み心地を確かめてみたい」という方は、トレーラハウスを利用した民泊に宿泊してみてください。
なお、民泊に関しては自治体ごとに各種制約があるため、始める前に条例を確認しておくことが欠かせません。
トレーラーハウスの税金の納付方法

トレーラーハウスの税金は、車両として認定されている場合は「自動車税」を、建築物として認定されている場合は「固定資産税」を支払います。
それぞれ、通知書が4月~6月に届き、支払い方法は以下の7つの方法があります。
- 市区町村の窓口
- 金融機関
- 口座振替
- クレジットカード
- コンビニ
- クレジットカード
- スマホ決済
- 電子マネー
市区町村の窓口は、現金支払いが可能で手数料がかかりません。クレジットカードや電子マネー・スマホ決済については、自治体によって取り扱いをしていない場合があります。
また、コンビニやスマホ決済・電子マネーを使用の際は、バーコードが付いている場合は使用できます。しかし、支払い上限が30万円となっているため、高額の場合は使用できないため注意が必要です。
トレーラーハウスの価格はどれくらい?

見た目にはインパクトがあり、節税効果も高いとなれば、トレーラーハウスを購入してみたいと考えるかもしれません。
トレーラーハウスの価格帯は幅広く、安価なものだと200万円代から販売されています。金額が安いものなら、初心者の方でも気軽に手を出しやすいかもしれません。
また、不要となったトレーラハウスはリセールすることも可能です。不要になったトレーラーハウスを売却し、自身の土地の方はその後の土地を、駐車場やマンション経営など、ほかの資産運用に切り替えしやすいでしょう。
トレーラーハウス購入時の注意点

これまで挙げてきたメリットによって「これはもうトレーラーハウスを購入するしかない!」ということを考える方もいるかもしれません。
しかし、購入の際は、次の2点に注意が必要です。
- 運搬が簡単ではない
- 設置場所には制限がある
運搬は簡単ではない
最初の注意点は「運搬が簡単ではない!」ということです。
トレーラーハウスを運搬する際は、直線で4m以上の幅員、カーブなどは7m又は交差点では双方7m以上の幅員を確保しなければならないため、事前の確認が必須です。
また、特殊車両通行許可を申請してから取得しなければなりません。しかし、取得までに3か月ほどかかる場合があります。
さらに、トレーラーハウスの重量に耐えうるだけのレッカー車が必要なため、自分が運転して運ぶことは難しくなっています。トレーラーハウスは、業者に運搬を依頼が必要ですが、約10万円の費用がかかります。
以上のように、時間と費用がかかるため、購入直後に簡単に移動できないと考えた方が良いでしょう。
設置場所には制限がある

「空いている土地があるし、とりあえず買ってそこに置けばいいか」ということを考えている方も注意が必要です。
トレーラーハウスはかなりの重量があるため、それに耐えられる地盤が必要です。
また、電気・水道の利用するためには、供給元や接続といった準備も欠かせません。
自治体によっては、トレーラーハウスの設置に対し、各種制限を設けていることも考えられます。
事前にしっかりと調査しておくことが、快適なトレーラハウス生活のカギを握ります。
まとめ:トレーラーハウスは設置方法によって節税対策は変わる!

この記事では、トレーラーハウスで節税できる理由を3点と注意点を紹介しました。トレーラーハウスは、車両として扱う場合と建物として扱う場合では、節税できるポイントが異なります。
車両として使用する場合は、固定資産税や自動車税の節税ができますが、移動させるときに費用がかかることを考慮しなければなりません。
建築物として利用する場合は、土地の固定資産税の節税が可能です。
また、トレーラーハウスは減価償却の期間が短く、投資目的として購入する方もいます。運用には条件があり、資産運用にはリスクを考慮しなければなりません。
この記事を参考にして、トレーラーハウスを使用する際は、うまく節税できるように活用してください。













